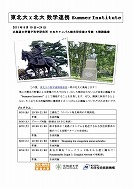WG番号:WG44
| 題目 |
複合材料における時空間パターンの予測と制御
|
| 期間 |
H 25.4.17~H26.3.27 |
| 責任者*と主な協力者 |
田﨑 創平*・義永 那津人
|
| 概略 |
合金などの複合材料において様々な相分離パターンが観測される。このような相分離の状況は材料の機能と密接に結びつく重要なものである。本ワーキンググループではその多様性を生み出すメカニズムを解明する。有用な数理モデルを構築し、適切な数値計算手法を確立することで、時空間パターンの精緻な予測と制御を目指す。望まれる機能材料を実現するための数理的発展研究の基盤を整備する。
|
| 活動報告 |
混合脂質膜における相互作用を研究した。国内外の生物物理・数理生物学研究者と討論を行い、脂質二重膜における基本的な相互作用効果を整理した。
- 平成25年9月14日 ゲッチンゲン大学数学教室において開催された HeKKSaGOn Satellite Workshop に参加し、特に最新の応用数学研究の情報を収集した。また、熱、弾性、化学反応、生物的運動等の相互作用効果の数理的側面を発表した。
- 平成25年9月14日—18日 ハイデルベルク大学 BioQuant に滞在し、主に脂質膜に関して、Anna Marciniak-Czochra 教授の研究グループと研究討論を行った。また、17日には BioQuant Seminar において、混合脂質二重膜に現れる微小ドメイン形成を弾性相互作用が安定化する数理的構造を発表した。
- 平成25年11月4日—8日 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所において開催された Forum “Math-for-Industry” 2013: The Impact of Applications on Mathematics に参加し、産業数学に関する最新の情報を収集するとともに、混合脂質二重膜における相互作用の数理を発表した。
- 学会発表
- 2013年4月30日 東北大WPI-AIMR, 第6回 Math Mate セミナー: 題目「相分離弾性系とその分岐・安定性解析」
- 2013年9月14日 ゲッチンゲン大学 数学教室 HeKKSaGOn Satellite Workshop 題目“Interactions between heat, phase, deformation, chemical reaction, and biological movement”
- 2013年9月17日 ハイデルベルク大学 BioQuant HeKKSaGOn Satellite Workshop 題目“Phase-separating elastic system of mixed lipid bilayers”
- 2013年9月17日 九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所Forum “Math-for-Industry” 2013: The Impact of Applications on Mathematics 題目“Phase-separating elastic system of mixed lipid bilayers”
- 論文
- Sohei Tasaki, “Interactions in Mixed Lipid Bilayers”, Proceedings of Mathematics for Industry 2013: The Impact of Applications on Mathematics, in press.
|
WG番号:WG40
| 題目 |
ソリトン理論とその応用研究 |
| 期間 |
H 25.4.22~H.26.3.31 |
| 責任者*と主な協力者 |
宮坂宥憲
|
| 概略 |
ソリトンは様々な物理現象に現れ、またその理論は数学やそれ以外の方面(代数幾何学や整数論、通信や素粒子論など)へ応用されている。WGでは様々な視点からソリトン理論(佐藤理論)を考察することで、新たな側面や応用を見出すことを目的とする。
|
| 活動報告 |
成果論文:
Torsion points on hyperelliptic Jacobians via Anderson’s p-adic soliton theory. (With T.Yamazaki) Tokyo Journal of Mathematics, 36 (2013), no.2, 387--403.
|
WG番号:WG48
| 題目 |
Joint Workshop on pure and applied mathematics 組織委員会
|
| 期間 |
H 25.7.5~H 25.11.02 |
| 責任者*と主な協力者 |
宮坂 宥憲*・中澤 嵩・中川 和重
|
| 概略 |
我々の社会における様々な問題に対して,数学が問題解決に対して直接貢献することは困難な場合がある.その理由は,環境や臨床医療といった一部の分野では,数学的な手法を活用する機会が少ないため,数学者と協働研究を遂行することが困難な場合があるからである.その際,数理科学の技術を多用する分野(工学,物理学等)の研究者と応用数学者が協働して,環境や臨床医療といった分野における問題解決を行ってきた.しかし,純粋数学・応用数学・異分野(環境,臨床医療,工学,物理学等)が連携して現実の問題に対処する事例は多くないように思われる.そこで,本WSでは,工学や物理といった異分野の研究者と純粋・応用数学者が研究発表を行うことで,純粋数学・応用数学・異分野が連携するための足がかりを作ることである.将来的には,異分野研究者と純粋・応用数学者が協働研究を進めるために必要な枠組みの構築が期待される.
|
| 活動報告 |
|
WG番号:WG42
| 題目 |
Workshop on nonlinear PDEs–PDE approach to network and related topics-
|
| 期間 |
H 25.4.22~H 25.7.30 |
| 責任者*と主な協力者 |
中川 和重*・長谷川 雄央・小池 茂昭
|
| 概略 |
ネットワーク上での偏微分方程式の研究は,情報・経済・生物ネットワークなどの問題の応用として現れる.一方で,ネットワークにおける完全非線形偏微分方程式の研究は新しい.本WSでは,完全非線形方程式に対するネットワーク上での研究の第一人者である F. Camilli 先生(Università Roma La Sapienza)を招聘し,これまでの研究のモチベーション及びこれまでの成果に対する連続講演を行ってもらう.また,ネットワークの研究で現れるPDE の研究を行っている研究者にも講演を依頼し,二つの見地からの研究を通じ,更なる研究への足がかりとする.さらに関連する講演を用意し,最新の結果の情報交換の場とする.
|
| 活動報告 |
述べ参加者数が当初予定を大幅に上回る54名(記名分)となった.その中で,多くの参加者が休憩時間を含め意見交換,議論を行っていた.本研究会は盛況のうちに終了した.
|
WG番号:WG39
| 題目 |
International workshop「Statistical approach to complex network」組織委員会 |
| 期間 |
H 25.4.15~H 25.9.11 |
| 責任者*と主な協力者 |
長谷川雄央*, 根本幸児, 矢久保考介, 高口太朗
|
| 概略 |
[Scope of the workshop]
Complex networks appear in a variety of contexts as, for example, social networks, WWW, financial networks, power supplying networks, etc. The workshop will bring together the researchers who are interested in how the phenomena emerging in these networks can be understood in terms of statistical physics, and give an opportunity to discuss most recent progress in the field. Topics of interest include (but are not limited to):
- Percolation model, Ising model, Potts model on Complex Networks
- Nonlinear Dynamics on Complex Networks
- Growing Networks organizing Criticality
- Cascade and Avalanche on Complex Networks
- Fractals and Self-similarities of Complex Networks
- Games on Complex Networks
- Transport and Communication on Complex Networks
[開催形式]
国内・国外より統計物理研究者、ネットワーク科学研究者を15名前後招聘し、2013年9月9日〜11日の期間、北海道大学学術交流会館にて開催する。招待講演者以外にもポスター発表者を広く募集する予定である。
|
活動報告 |
2013年9月9日〜11日、北海道大学学術交流会館にて開催した (なお、研究会のタイトルは「International Workshop on Phase Transition, Critical Phenomena, and Related Topics on Complex Networks」に変更された)。14件の招待講演(下記リスト参照)と18件のポスター発表で構成され、参加者は49名となった。本研究会を組織する際、複雑ネットワーク上の数理モデルの相転移・臨界現象をキーワードに招待講演者を選んだ。複雑ネットワークに関わる研究会は国内外問わず数多く行われているが、その中でも特色のある研究会となったと考えている。また、この研究会はネットワーク科学としてネットワークを研究している研究者、統計物理(特にランダム系の文脈において)ネットワークを研究している研究者をミックスさせ、二つの領域の研究の交流と今後の融合的研究のきっかけとなりうる会とすることを目的とした。実際研究会では学生スタッフ問わず、参加者間で熱心な議論が生まれ、上記の目的を達成することができた。
招待講演者:
- Araujo, N (ETH Zurich, Switzerland)
- Gastner, M (University of Bristol, UK)
- Goh, K-I (Korea University, Korea)
- Hasegawa, T (Tohoku University, Japan)
- Hukushima, K (University of Tokyo, Japan)
- Kabashima, Y (Tokyo Institute of Technology, Japan)
- Kim, B J (Sungkyunkwan University, Korea)
- Masuda, N (University of Tokyo, Japan)
- Nogawa, T (Toho University, Japan)
- Reichardt, J (University of Würzburg, Germany)
- Son, S W (Hanyang University, Korea)
- Takaguchi, T (National Institute of Informatics, Japan)
- Tanizawa, T (Kochi National College of Technology, Japan)
- Yakubo, K (Hokkaido University, Japan)
*本会議のために集められたプロシーディングスは北海道大学トポロジー理工学教育研究センターの発刊する雑誌「Topologica」にて出版される予定である。
|
WG番号:WG41
| 題目 |
文科省ワークショップ「応用現代幾何学」組織委員会 |
| 期間 |
H 25.4.8~H 25.9.5 |
| 責任者*と主な協力者 |
三浦佳二*・尾畑伸明
|
| 概略 |
数学を応用する諸分野(数理科学)においては、慣習的になった数学手法を使うのみならず、誰も使っていない純粋数学のアイデアをいち早く取り入れることで、イノベーションが期待される。事実、欧米においては、高度で抽象的な数学も潜在的に強力な道具になりうることが良く理解されており、直感を超えるレベルのトポロジーや微分幾何学を応用した研究も盛んである。そこで、日本ではまだ弱い「応用現代幾何学」の分野において、
のマッチングを目指す野心的な勉強会を開催する。純粋数学から応用まで広い分野から講演者・参加者を募って、なるべく堅苦しくない勉強会とする。
- 応用側の講演者には、幾何学を役立てている内容の講演を短めにお願いして、数学に対するニーズを挙げて頂く。
- 純粋数学側の講演者には、応用できそうな曲線・曲面・トポロジーの講演をお願いする。数学を使う応用分野の研究者の中でも特に数学が得意と自負する猛者に聴衆として集まってもらって、何かしら応用への接点を発掘してもらう。また、一般向けの基調講演の形にすることで、異分野の数学者にも役立つことを期待している。
応用分野においては、必ずしも数学の強い背景を持たない人も多く、既存の数学手法のみに頼りがちである。純粋数学者の成果を理解するのはなかなか難しいが、それを理解する応用数学者等を介して伝えていくことで、諸分野において適切に使われるようになることが望ましい。さながらバケツリレーとも言える、この数学連携活動の流れを円滑にすることが、本研究集会の目的である。
|
活動報告 |
SMART研究会「応用現代幾何学」場所:情報科学研究科棟2F大講義室
http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~smart/forum/index.html#AMG2013
9月3日
- 13:00-13:10
開会あいさつ
- 亀山充隆(東北大学大学院情報科学研究科長)
- 粟辻康博(文部科学省基礎研究振興課融合領域研究推進官)
- 13:15-14:45
飯高茂(学習院大学理学部名誉教授),
「Kodaira dimension and mixed plurigenera of algebraic varieties」
- 15:15-15:45
松江要(東北大学大学院理学研究科,
「ホモロジーによる非晶質の特徴付け」
- 16:00-17:00
正宗淳(東北大学大学院情報科学研究科,
「米国における橋渡し人材を育てる応用数学教育」
9月4日
- 09:00-09:30
張山昌論(東北大学大学院情報科学研究科)
「曲率に基づいたチューブ状構造要素の抽出と医用画像処理への応用」
- 09:30-10:00
三浦佳二(東北大学大学院情報科学研究科)
「グラフ上の流れのHodge-小平分解入門」
- 10:15-11:45
清水勇二(国際基督教大学教養学部)
「数え上げ幾何と応用 -- 曲線の数え上げ --」
- 13:15-14:45
五十嵐悠紀(筑波大学システム情報系))
「デジタルデザイン技術を活用した手芸と工作」
- 15:00-16:30
落合啓之(九州大学マス・フォア・インダストリ研究所)
「行列の数理と運動の記述」
- 16:45-18:15
下川航也(埼玉大学理工学研究科)
「結び目理論の分子生物学への応用」
9月5日
- 09:00-09:30
長谷川雄央(東北大学大学院情報科学研究科)
「グラフの双曲性から見る相転移」
- 09:30-10:00
近藤剛史(東北大学大学院理学研究科)
「双曲群とは」
- 10:15-11:45
玉木大(信州大学理学部)
「本当にモデル圏でいいのか?」
- 13:15-14:45
井ノ口順一(山形大学理学部)
「可積分幾何・差分幾何」
- 14:45-15:00
閉会あいさつ,
尾畑伸明(東北大学大学院情報科学研究科)
キーワード:
小平次元、Hodge-小平分解、Gromovの幾何学的群論、可積分幾何、微分形式、結び目理論、ホモロジー、数え上げ幾何、その他。特筆すべき点として、日本人初のフィールズ賞受賞者である小平邦彦氏が作り上げた数学が、ようやく諸分野において広く使われる段階へと入ってきたことについても議論した。
|
WG番号:WG45
| 題目 |
非可換解析の諸分野への応用
|
| 期間 |
H 25.6.10~8月31日 |
| 責任者*と主な協力者 |
尾畑伸明*・田中太初・廣島文雄・洞彰人・今野紀雄・山上滋
|
| 概略 |
量子確率論、量子ウォーク、場の量子論、代数的組合せ論などで議論されている様々な非可換構造について、代数学・組合せ論・確率解析が協働できる議論の場を提供する。現象の背後にある非可換構造を明らかにし、その表現を通して実際の現象を理解する方法論について議論を深め、その可能性をさまざまに探る。
|
活動報告 |
北海道大学理学部4号館にて8/5-8/7で「International Workshop on Noncommutative Analysis and its Future Prospects」
と題する国際研究集会を開いた。
http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata/seminar/SapporoWS-2013/Sapporo-2013.htm
8月5日
- 10:00-10:50
Marek Bożejko (University of Wrocław, Poland),
「Generalized Gaussian processes and positive definite functions on permutations groups」
- 11:00-11:50
Zied Ammari (Université de RennesI, France),
「De Finetti theorems and their applications to the mean field problem」
- 11:00-11:50
Un Cig Ji (Chungbuk National University, Korea),
「Differential equations in quantum white noise theory」
- 13:30-14:15
Izumi Ojima (Kyoto University, Japan),
「Geometry of symmetry breaking」
- 14:20-15:10
Luis Velazquez (Universidad de Zaragoza, Spain),
「Quantum recurrence and Schur functions」
- 15:20-15:50
Takao Namiki (Hokkaido University, Japan),
「The Baker's transformation and quantum walk」
- 15:50-16:20
Etsuo Segawa (Tohoku University, Japan),
「Limit behavior of quantum walks on half line related to orthogonal polynomials」
8月6日
- 10:00-10:50
Marek Bożejko (University of Wrocław, Poland),
「Generalized Gaussian processes and positive definite functions on permutations groups」
- 10:00-10:50
Christian Gérard (Université Paris-Sud, France),
「Construction of Hadamard states by pseudo differential calculus」
- 11:00-11:50
Un Cig Ji (Chungbuk National University, Korea),
「Differential equations in quantum white noise theory」
- 13:45-14:30
Asao Arai (Hokkaido University, Japan),
「Asymptotic expansions in the coupling constant for the ground stateenergy of the generalized spin-boson model」
- 14:35-15:20
Itaru Sasaki (Shinshu University, Japan),
「Multiplicity of eigenvalues of the non-commutative harmonic oscillator」
- 15:30-16:15
Hiroaki Yoshida (Ochanomizu University, Japan),
「Applications of dissipation formulas of the relative free entropy」
- 16:20-17:05
Kenichiro Tanabe (Hokkaido University, Japan),
「A generalization of twisted modules over vertex algebras」
8月7日
- 10:00-10:50
Demosthenes Ellinas (Technical University of Crete, Greece)
「Phase plane operator valued probability measures: Constructions and random evolution」
- 11:00-11:50
Tullio Ceccherini-Silberstein (Università degli Studi del Sanniodi Benevento, Italy)
「Advanced Mackey theory for finite groups」
- 13:30-14:15
Hiroshi Mizukawa (National Defense Academy of Japan)
「Interactions between Ehrenfest's urns arising from group actions」
- 14:20-15:05
Tatsuya Tate (Tohoku University, Japan)
「The Hamiltonians generating one-dimensional discrete-time quantum walks」
- 15:10-15:55
Tatsuro Ito (Kanazawa University, Japan)
「TD-algebras at q=1」
|
WG番号:WG8
| 題目 |
脳型情報処理 |
| 期間 |
H23.4.1~H25.5.13 |
| 責任者*と主な協力者 |
三浦佳二*・林初男・中田 一紀 |
| 概略 |
結合位相振動子の理論を応用したアナログデジタルコンバータなど、神経回路網の数理から学んだ機能的集積回路の実現を目指す。 |
| 活動報告 |
神経細胞のネットワークからなる数理モデルを、集積回路として実現することで、
- 非線形発振回路の雑音誘起同期現象
- ワイヤレスセンサーネットワークの同期プロトコル
- ディレイフィードバックのある中でのロボットの歩行の制御
- 最適な同期特性を持つニューロンモデルの設計
- 形状非依存的なタッチカウンター
を実現した。この成果を国際会議の会議録として査読付き論文7本を出版した。
- 学会発表(プロシーディングス有)
- 平成23年11月28日~12月2日,
IUTAM Symposium on 50 Years of Chaos: Applied and Theoretical, Kyoto.
Kazuki Nakada, Keiji Miura, Hatsuo Hayashi,
“Noise-induced Phenomena in Two Strongly Pulse-coupled Resonate-and-Fire Neuron Models”
The proceedings of IUTAM Symposium of 50 years of Chaos (Procedia IUTAM)(査読有り)
- 平成24年1月19日~1月20日,
電子情報通信学会 回路とシステム研究会(CAS)
中田一紀,三浦佳二,浅井哲也,
「位相縮約による非線形発振回路の雑音誘起同期現象の数理解析」
信学技報, vol. 111, no. 377, CAS2011-101, pp. 89-94, 2012年1月.(査読無し)
- 平成24年10月5日
電子情報通信学会 ニューロコンピューティング研究会(NC)
中田一紀,三浦佳二,浅井哲也,
「位相縮約に基づくシリコンニューロンのダイナミカルシステムデザイン」
信学技報, vol. 112, no. 227, NC2012-60, pp. 139-144, 2012年10月.(査読無し)
- 平成24年11月14日
ICONIP2012
Kazuki Nakada, Keiji Miura,
"Clock Synchronization Protocol using Resonate-and-Fire Type of Pulse-coupled Oscillators for Wireless Sensor Networks"
The ICONIP 2012 proceedings, Part V, Lecture Notes in Computer Science series 7667, pp. 629-36.(査読有り)
- 平成24年11月20日~11月24日
SCIS-ISIS2012にて、セッション「Mathematical Modeling of Neural Systems」を企画し以下の3件の発表を行った.
- Keiji Miura,
“Effects of Noise Correlations on Population Coding”
- Keiji Miura, Kazuki Nakada,
“Synchronization Analysis of Resonate-and-Fire Neuron Models with Delayed Resets”
- Kazuki Nakada, Keiji Miura, Tetsuya Asai,
“Silicon Neuron Design based on Phase Reduction Analysis”
(査読有り、計3本)
- 平成24年12月2日~12月5日
The 2012 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS)
Kazuki Nakada, Keiji Miura, Tetsuya Asai, Hisa-aki Tanaka
" Dynamical Systems Design of Nonlinear Oscillators using Phase Reduction Approach"(査読有り)
- 平成25年7月3日~7月7日
IEEE EMBC2013
Kazuki Nakada, Keiji Miura, Tetsuya Asai
“Dynamical System Design for Silicon Neurons using Phase Reduction Approach”(査読有り)
- 学会発表(プロシーディングス無)
- 平成24年3月8日~3月9日
日本応用数理学会 数理設計研究部会(九大)
中田一紀, 三浦佳二, 浅井哲也,
「位相縮約法に基づく非線形発振回路の最適化設計」
- “平成24年4月6日 SMARTセミナー
「時間遅れを含む微分方程式の周期解の位相縮約」
- 平成24年10月12日
SMARTセミナー
「Synchronization Analysis of Neuronal Oscillators」
- 平成25年3月19日
CREST-SMART 年次報告会
「形状非依存的なタッチカウンターの並列神経回路による実装」
-
平成25年8月4日~8月9日
IJCNN 2013
Kazuki Nakada, Keiji Miura and Hiroaki Wagatsuma
“Phase Response Curves Explain How Multiplicative Feedback on Neural Phase Elements Differs from Adaptive Physical Feedback in Robotic Motion Controls”
|
WG番号:WG37
| 題目 |
九大IMI 短期共同研究「量子ウォークの新展開:物質制御へのアプローチ」組織委員会 |
| 期間 |
H 25.3.25~H 25.6.21 |
| 責任者*と主な協力者 |
瀬川悦生*・尾畑伸明・松岡雷士
|
| 概略 |
レーザー量子制御の産業応用を目指す研究者とQW数理の研究者の混成チームによって、これまで抽象的な系で議論されてきたQWによる基本原理をレーザーによる分子状態制御についての応用上の問題へ展開する。また、量子ウォークの画像処理への応用や開放系量子ウォークの関係性についても議論する。
|
活動報告 |
平成25年6月17日-21日、九州大学マスフォアインダストリ研究所・短期共同採択研究にて"量子ウォークの新展開:物質制御へのアプローチ" と題する研究会を開催した。
http://www.imi.kyushu-u.ac.jp/joint_research/detail/20130001
6月17日
- 10:00~10:30
Akira Ichihara (Japan Atomic Energy Agency)
「An analytic expression to evaluate rotational transition processes of diatomic molecules in an optical frequency comb」
- 10:40~11:10
Leo Matsuoka (Japan Atomic Energy Agency)
「Developing an analytical model for evaluating imperfect rotational excitation cascade of molecules in a slightly detuned optical frequency comb」
- 15:00~15:50
Etuo Segawa (Tohoku University)
「Mapping theories of quantum walks」
6月18日
- 10:30~12:00
Keiichi Yokoyama (Japan Atomic Energy Agency)
「Studies for isotope separation based on the quantum control of molecules」
- 13:20~14:50
Norio Konno (Japan Atomic Energy Agency)
「An introduction to quantum walk and its applications」
6月19日
- 10:00~11:00
Yusuke Ide (Kanagawa University)
「Continuous time quantum walks on some graphs」
- 11:10~12:10
Hyun Jae Yoo (Hankyong National University, Korea)
「Large deviation principle for Markov chains and some applications」
6月20日
- 10:30~12:00
Salvador E. Venegas-Andraca (Tecnologico de Monterrey Campus Estado de México and Disruptive Computer Technologies, SA de CV)
「Quantum walks: a concise review with emphasis on quantum walk-based algorithms, computational universality and potential applications」
- 13:20~14:20
Salvador E. Venegas-Andraca (Tecnologico de Monterrey Campus Estado de México and Disruptive Computer Technologies, SA de CV)
「Quantum Image Processing and Quantum walk-based Morphological Operators」
6月21日
- 10:00~11:00
Tatsuaki Wada (Ibaraki University)
「Anomalous slow diffusion in nonlinear quantum walk」
- 11:10~12:10
Yutaka Shikano (Institute for Molecular Science)
「How to implement the discrete time quantum walk in the hybrid quantum system?」
|
WG番号:WG32
| 題目 |
ガラスとその周辺の非平衡現象 |
| 期間 |
H 24.5.25~H25 3.25 |
| 責任者*と主な協力者 |
能川知昭*
|
| 概略 |
広い意味でのガラス現象の理解に以下のような側面からアプローチする。
- WPI-AIMRの金属ガラスの実験グループと議論し、アモルファス状態の構造解析などを通してランダムネスが自発的に生成されるメカニズムの理解を計る。またそれによって、より良い機能材料の開発を目指す。
- 「ガラス的」と呼ばれる遅い緩和現象には多くのバリエーションが存在するが、それらに共通するメカニズムと考えられているものに「相互作用のフラストレーション」がある。これに関して、抽象・単純化された数理モデル(例えばFrustrated XY model)の理解を深めると同時に構造ガラスとの対応関係について考察する。ここでは数学の分野との研究協力を模索する。
- 近年ガラス転移のrandom first order theoryと呼ばれる概念が提唱され、ガラス形成物質のアルファ緩和と過飽和蒸気のような準安定状態の緩和過程との類似性が指摘されている。しかし後者のような比較的単純な状況においてさえ、有限次元系の準安定性の起源についての明瞭な説明は存在しない。これは非平衡基礎論の難題であるが、その解決の手がかりを模索する。
|
| 活動報告 |
- 2012年5月31日 東北大WPI-AIMR,
第3回非平衡スタディグループにてセミナー。
題目「Josephson接合配列におけるjamming転移」
- 2012年6月7日 東北大学工学研究科,
応用物理専攻佐々木研究室にてセミナー
題目「irrationally frustrated XY modelにおけるjamming転移」
- 2012年6月29日 東北大学WPI-AIMR,
WPI-AIMR Workshop“Structure and Dynamics of Glass -Bridging mathematics and material science-”に参加、講演
題目 “Jamming transition in superconductor”
- 2012年8月1日-4日 京都大学基礎物理学研究所,
研究会「非平衡系の物理 -その普遍的理解を目指して-」に参加、4日発表。
題目「非平衡状態における等重率の仮定の有用性: Pottsモデルの定温緩和における検証」
- 2012年9月3日-7日 東北大学WPI-AIMR,
研究会“Random Meida II”に参加、6日講演。
題目 “Diffusion and sliding dynamics of elastic and plastic manifolds in random media”
- 2012年11月16日 青山学院大学,
物理・数理コロキウムにてセミナー。
題目「磁場中Josephson接合配列におけるjamming転移の特異性」.
- 2012年12月14日-16日 東北大学,
研究会「情報統計力学の最前線」に参加、14日講演。
題目「緩和過渡状態に等重率分布を仮定した粗視化ダイナミクス」
- 2013年1月11日 東北大学,
「ガラス討論会」を開催、講演
講演者と題目
吉野元「ガラスのレプリカ理論 」,
藤田武志「応力誘起ガラス相転移」,
平田秋彦「金属ガラスの構造」,
藤田武志「自由エネルギー地形の可視化」,
能川知昭「random packing」
- 2013年1月18日Oakridge National Laboratory,
“Workshop on glass and mathematics”に参加、講演。
題目“Numerical search of closely packed droplets of multicomponent particles
- 2013年2月18日 東北大学,
WPI-AIMR Workshop “Structure and Dynamics of Metallic Glass”に参加、講演。
題目”Polydispersity Effect on Solid-Fluid Transition in Hard Sphere Systems”
- 2013年3月7日 東北大学,
第八回ミーティング:数学+物性理論+物性実験にてセミナー。
題目「磁場中Josephson接合配列におけるjamming転移の特異性」
原著論文
- “Transition by Breaking of Analyticity in the Ground State of Josephson Junction Arrays as a Static Signature of the Vortex Jamming Transition”, Tomoaki Nogawa, Hajime Yoshino and Bongsoo Kim, Phys. Rev. E 85, 051132 (2012):1-5.
- “Usefulness of equal-probability assumption for out-of-equilibrium states: a master equation approach”, Tomoaki Nogawa, Nobuyasu Ito and Hiroshi Watanabe, Phys. Rev. E 86. 041133 (2012).
|
WG番号:WG28
| 題目 |
構成的手法による非線形分散型方程式の大域解析WG |
| 期間 |
H 24.4.1~H 25 3.19 |
| 責任者*と主な協力者 |
前田昌也*・瀬片純市
|
| 概略 |
非線形シュレディンガー方程式、KdV方程式、Zakharov方程式を含む非線形分散型方程式の大域解を終値問題を解くことにより構成する。特に爆発解、散乱+ソリトン解の構成を通して非線形分散型方程式の解の大域挙動の理解を深める。
|
| 活動記録, 成果 |
ポテンシャル中を運動するソリトンの漸近安定性についてCuccagna氏(Trieste Univ.)との共同研究を行った. この研究では従来は有限時間にとどまっていたソリトンのダイナミクスの解析を解析力学の手法と漸近安定性理論を組み合わせることにより時間無限遠まで行うことができた. この結果はさらに低次元やグラフ上での拡張を模索することにより様々な応用があると考えられる.
- 2012年4月:ハミルトン偏微分方程式のソリトン解の漸近安定性に関する論文(単著)
“Stability of bound states of Hamiltonian PDEs in the degenerate cases”
が Journal of Functional Analysis に採録決定.
- 2012年5月‐7月:イタリア・トリエステ大学のCuccagna氏を訪問し定在波解の漸近安定性理論について意見を交換した。
Cuccagna氏とはソリトンの漸近安定性に関連したプレプリント
“On weak interaction between a ground state and a nontrapping potential” (submitted)
を投稿.現在, このプレプリントを発展させたものを研究中.
- 2012年9月:鈴木香奈子氏(茨城大学)との細い領域でのピーク解についての論文
“Concentration of least-energy solutions to a semilinear Neumann problem in thin domains”
を投稿.
- 2012年10月
岸本展氏(京都大学)との共同研究
“Construction of blow-up solutions for Zakharov system on T^2”
が Annales de l’Institut Henri Poincaré - Analyse non linéaire
に採録決定. http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/02941449
-
8月29日(水)10:00~8月30日(木)15:50:「Workshop on Nonlinear Dispersive PDEs」を開催.
@東北大学大学院理学研究科合同A棟801号室
August 29 (Wed)
- 10:00~10:50 Norihisa Ikoma (Tohoku University) On behaviors of minimizing sequences for some nonlinear Schrodinger system
- 11:00~11:50 Tadahiro Oh (Princeton University) Invariant weighted Wiener measure for the derivative NLS
- 14:00~14:50 Tomoyuki Niizato (Osaka University) Almost global existence of solutions to the Kadomtsev-Petviashvili equations
- 15:00~15:50 Kotaro Tsugawa (Nagoya University) Unconditional well-posedness of the fifth order modified KdV equation with periodic boundary condition
- 16:00~16:50 Soonsik Kwon (KAIST) On the fifth-order KdV equations
August 30 (Thu)
- 10:00~10:50 Masashi Aiki (Keio University) Motion of a vortex filament with axial flow in the half space
- 11:00~11:50 Tadahiro Oh (Princeton University) On the Cauchy problem of the one-dimensional cubic NLS in the low regularity setting
- 14:00~14:50 Kohei Soga (Waseda University) Stochastic and variational approach to finite difference methods
- 15:00~15:50 Ryo Takada (Kyoto University) Dispersion phenomena in the rotating Navier-Stokes equations
- 口頭発表
- ``On the solution of nonlinear elliptic equation in a thin domain'',
第37 回偏微分方程式論札幌シンポジウム, 北海道大学, 2012年8月.
- ``On the weak interaction between soliton and non-trapping potential",
応用数学セミナー, 東北大学, 2012年10月.
- ``Nonexistence of minimal mass blow-up solution of Zakharov system on 2D
torus", 第7回非線形偏微分方程式と変分問題, 首都大学東京, 2013年2月.
- ``Nonexistence of minimal mass blow-up solution of Zakharov system on 2D
torus", 研究集会「若手のための偏微分方程式と数学解析」, 福岡大学セミナ
ーハウス, 2013年2月.
- ``Nonexistence of minimal mass blow-up solution of Zakharov system on 2D
torus", 第5回名古屋微分方程式研究集会, 名古屋大学, 2013年3月
|
WG番号:WG36
| 題目 |
RCPAM-CMRU研究会「Quantum walks and dynamics on metric graphs」組織委員会 |
| 期間 |
H 25.1.18~H25.3.7 |
| 責任者*と主な協力者 |
瀬川悦生*・福泉麗佳・前田昌也 |
| 概略 |
メトリックグラフ上のダイナミクスに関して、 量子ウォーク、量子グラフ、確率論、非線形シュレディンガー方程式などの視点から話題を提供してもらい、 基本的な概念を共有することで、その結びつきを参加者で議論し、知見を掘り下げて行く。
|
| 活動報告 |
平成25年3月7日、東北大学情報科学研究科棟6F小講義室にて"Quantum Walks and
Dynamics on Metric graphs" と題するワークショップを開催した。
- 13:00~13:50
今野 紀雄 (横浜国立大学)
「A universality class of quantum walks」
- 14:00~14:50
Riccardo Adami (Politecnico di Torino, Italy)
「Stability for the ground state of the NLS on star graphs」
- 15:00~15:50
楠岡 誠一郎 (東北大学)
「Diffusion processes in thin tubes and their limits on graphs」
- 16:00~16:50
鹿野 豊 (自然科学機構 分子科学研究所)
「Nonlinear quantum walk and porous medium equation」
|
WG番号:WG35
| 題目 |
「双曲系の数理」勉強会 |
| 期間 |
H25 1.8~H25 3.7 |
| 責任者*と主な協力者 |
能川知昭* |
| 目的 |
双曲格子、複雑ネットワーク上のランダムウォーク、パーコレーションといった模型に現れるグラフの双曲性の問題をひとつの接点として、統計物理学と、確率論、離散幾何、幾何学的群論といった数学の分野の交流、融合を計る。双方の分野の研究者が交互に講演を行い、問題意識や目指すものの相互理解を得ることが初段階の目的である。 |
| 活動報告 |
学外講演者も招く研究会の開催に向けて、東北大学所属研究者によって勉強会を行った。講演タイトルは以下の通り。講演時間は各90-120分で活発な議論・討論が行われ、異分野研究者の共通認識を形成するきっかけづくりに成功した。
- 能川知昭 「無限グラフ上の相転移‐くりこみ群による理解‐」
- 長谷川雄央「Cheeger constant, hyperbolicity, traffic flowについて」
- 瀬川悦生「自由群と可換群上の量子ウォークの解析に向けて」
- 田中亮吉「無限グラフ上のランダムウォーク」
- 近藤剛史「等周スペクトラムから見た双曲群」
|
WG番号:WG34
| 題目 |
研究会「ポテンシャル論に現れる逆問題と求積公式」 |
| 期間 |
H24.12.18~H25 3.3 |
| 責任者*と主な協力者 |
小野寺有紹*・宗政昭弘 |
| 目的 |
求積公式に関連する研究は, 様々な分野において独自の方向性をもって発展しており, 共通点の多い対象を研究しているにも関わらず, なかなか互いに接点を持てない状況にある. 本研究集会を通し, 各々の分野で活躍する研究者を集め, 分野横断的に互いの研究に対する理解を深める. 特に, 長期的な目線での研究発展を目標とし, それぞれの研究動向やアイディアを共有することを主眼とする. |
| 活動報告 |
以下の研究集会を開催:
研究集会タイトル:ポテンシャル論に現れる逆問題と求積公式
日程:2013年3月3日(日)
場所:東北大学大学院情報科学研究科中講義室
講演者:緒方秀教 (電気通信大学), 平尾将剛 (東京女子大学), 小野寺有紹 (九州大学)
|
| 活動成果 |
本研究集会では, 求積公式というキーワードをもとに異なる分野の講演者を集め分野横断的な討論を行った. 今回は互いの分野のアイディアや研究意識を共有することを目標としたが, それぞれの講演者, そして参加者が異なるバックグランドを持っているという特徴的な研究集会であったものの, 講演者が平易な解説を試みたこと, また聴衆が積極的に討議に参加したことによって, 大成功したといえる. 特に, それぞれの研究の共通点を把握することができた本研究集会は, 今後の新しい研究発展に寄与できるものと期待される. 同様の研究集会を継続的に開催することで, 分野横断的な研究発展を目指したい. その意味でも, 本研究集会はよいスタートとなったものといえる.
|
WG番号:WG12
| 題目 |
幾何学的保存則による界面運動の解析 WG |
| 期間 |
H23.4.7~H24 12.18 |
| 責任者*と主な協力者 |
小野寺有紹* |
| 概略 |
Hele-Shaw流に現れる界面運動は, 複素モーメントと呼ばれる幾何学量が時間に対して不変量となることが示されている. 他の界面運動に対し, このような大域的な数学的構造に着目することで, 新しい視点からの解析的アプローチを導入し発展させる |
| 活動報告 |
Hele-Shaw流を特別な場合として含むモーメント保存則から自然に導かれる幾何学流モデルを導出することができた. 特に, Hele-Shaw流が領域に関するモーメントを保存するに対し, 我々が構成した一般のモデルのひとつは, 領域ではなく, 境界という余次元1の超曲面のモーメントを保存する. このモデルは純数学的なものであり, それ自体が他の自然科学で現れるかは定かではないが, それが持つ性質であるモーメントの保存則は電磁気学や重力場の理論において多様な応用が期待される. 特に, 我々の研究の成果として, このモデルが数学的に一意に解を有することを示した. これは, モデルが数学的にも意味を持つことを示している.
- 2011年7月25-27日: 京都大学で開催されたRIMS共同研究「微分方程式に対する幾何解析の展開」に参加, 講演. 講演タイトル「Hele-Shaw流における自由境界の漸近挙動について」.
- 2011年9月1日-12月15日: Institut Mittag-Leffler において開催された研究プログラム“Complex Analysis and Integrable Systems”に参加. 滞在期間中に同研究所で開催された研究集会“Operator Theory and Integrable Systems”において講演. 講演タイトル“Stability of a Hele-Shaw flow with two point sources in Hölder spaces”.
- 2011年12月17, 18日: 東北大学で開催された研究集会“Winter School in Sendai 2011 -- Complex Analysis Approaches to Free Boundary Problems”に参加, 講演. 講演タイトル“Theory of quadrature domains applied to the Laplacian growth”.
- 2011年12月20日: 台湾のNational Center for Theoretical Sciences において開催された研究集会“2011 Taiwan-Japan Joint Workshop on PDEs and Geometric Analysis”に参加, 講演. 講演タイトル“Stability of quadrature domains under Hele-Shaw evolution with two point sources”.
- 2012年2月17日: 北海道大学で開催された第13回北東数学解析研究会に参加, 講演. 講演タイトル“A moment-preserving flow for surfaces”.
- 2012年2月28日-3月4日: ESF-JSPS Frontier Science Conference for Young Researchers “Mathematics for Innovation: Large and Complex Systems”に参加, 講演. 講演タイトル“Stability of quadrature domains under Hele-Shaw evolution”
- 2012年3月13日: 組織委員として研究集会“SMART Workshop: Exploring Collaborative Mathematics”を東北大学にて開催, 講演. 講演タイトル“A new geometric flow of surfaces and its applications”.
- 2012年7月1日: アメリカ, フロリダ州で開催された9th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications に参加, 講演. 講演タイトル“A moment-preserving flow for surfaces and its applications”.
- 2012年7月30日: 北海道大学で開催された Summer School “Variational Methods for Evolving Objects”に参加, ポスター発表. 発表タイトル“A moment-preserving flow applied to a variational problem in potential theory”.
- 2012年8月11日: 岐阜大学で開催された第1回岐阜数理科学研究会に参加, 講演. 講演タイトル「ポテンシャル論に現れる変分問題と対応する幾何学的発展方程式」.
- 2012年9月20日: 九州大学で開催された日本数学会2012年度秋季総合分科会に参加, 講演. 講演タイトル「変分問題と対応する幾何学的発展方程式」.
- 2012年11月7日: 京都大学数理解析研究所で開催されたRIMS研究集会``Geometry of solutions of Partial Differential Equations''に参加, 講演. 講演タイトル“A geometric flow for quadrature surfaces”
|
WG番号:WG26
| 題目 |
Young Scientist Meeting of Statistical Physics and Information Processing (YSM-SPIP) 2013組織委員会 |
| 期間 |
H 24.4.9~H 24.12.26 |
| 責任者*と主な協力者 |
安田 宗樹*・長谷川 雄央・大関 真之・杉山 友規
|
| 概略 |
本研究会YSM-SPIP(Young Scientist Meeting of Statistical Physics and Information Processing)は、統計力学と情報科学の接点を深めよう、お互いの領域の垣根を越えよう、という意図の下、若手研究者によって2010年より企画/実行されてきた研究会である。ここ20年ほどの間に、情報科学の諸問題に統計力学的手法でアプローチする研究が盛んになってきた。この領域横断的な取り組みを標語的に情報統計力学と呼ぶ。本研究会は、情報統計力学に関連した各分野で精力的に活動している若手研究者を募集し、多岐にわたる個々の分野での現在進行形の発展を持ち寄り、今後の可能性を模索する事を意図している。特に、研究会を通じて関連分野の若手研究者間の交流を促進させ、各々のアイデアをぶつけ合う機会を設けることで、若手研究者の持つ研究シーズを研究レベルまで成長させることを目的とする。
本研究会は過去東京工業大学(2010年)、大阪大学(2011年) 、京都大学(2012年)にて開催されてきた。本WGでは平成24年度の本研究会を組織する。東北大学の関連研究者を含め多くの研究者の参加を促し、研究会運営をもって今後の当該分野の拠点形成を目指す。
|
| 活動報告 |
2012年12月14日-16日の期間、東北大学・情報科学研究科棟大講義室・中講義室にて開催した。INRIA(フランス国立情報学自動制御研究所)のCyril Furtlehner氏を含む9名を講師として招聘した他、21(8+13)件の一般講演・ポスター講演が設けられた。研究会の合計参加者数は57名となった。統計物理学と情報科学の若手研究者が相互に意見や発想を交わし合い、本研究会の目標である学際的境界領域の中での分野開拓のための連携関係をいっそう強めることができた、また、研究拠点としての東北大学の存在感をアピールできたと考えられる。
|
| 備考 |
過去の開催記録を含めた情報は下記HPに記載:
http://www-adsys.sys.i.kyoto-u.ac.jp/mohzeki/YSMSPIP/index.html
|
WG番号:WG27
| 題目 |
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 短期共同研究「光ファイバーとそれに関連する非線形偏微分方程式の研究」組織委員会 |
| 期間 |
H 24.4.9~H 24. 11.21 |
| 責任者*と主な協力者 |
前田昌也*・尾畑 伸明 |
| 概略 |
近年のインターネットの発達に伴い光ファイバーは社会においてますます重要性を増している。光ファイバー中のパルスは非線形シュレディンガー方程式 (NLS) により近似にされると考えられていることから、NLSのダイナミクスに関する詳細な研究は非線形光学の立場からもますます必要とされてきている。1980年代より始まったNLSの関数解析的なアプローチによる研究は未だ数多くの問題が残されているものの一段落しており、現在ではNLSに外力項、確率項、ダンピング項などをつけたり、光ファイバーを一次元ではなく細い高次元領域としたりすることにより、より現実に近いと考えられるモデルを研究することが主流になりつつある。
以上のように光ファイバーに関するNLSの研究は徐々に広がりを持ち始めてきている。そこで、本共同研究における目的は広がりつつある様々なモデルのNLSの研究者を集め、横につながった専門家達の間で議論すると同時に、数値計算の専門家ならびに産業界より専門家を招き、NLSの数学的研究と光ファイバーなどへの応用の関係を明確にするという縦の議論を行うことにある。これにより現在までに各々のNLSに対して洗練、特化されてきた手法が数値計算、産業界の専門家を通じて実際の光ファイバー中のパルスの制御に役立つことが期待される。
本共同研究は数学の専門家だけで議論しがちであったNLSの研究を数値計算、産業界の専門家を加えることにより基礎から現実への応用まで見据えながら行う今までなかったものであり、産業界側が最先端の数学の手法を取り入れるだけでなく、数学側にも新たな問題意識を作るというメリットがある。
|
| 活動記録 |
8月20日
- 13:30~15:00 鈴木香奈子(茨城大学) 「ある反応拡散方程式系における基礎生産項の役割について」
- 15:30~17:00 千葉逸人(九州大学) 「線形作用素の一般化スペクトル理論とその無限次元力学系への応用」
8月21日
- 10:00~11:30 眞崎聡(学習院大学)「光ファイバーに由来する非線型方程式の解の大域挙動について」
- 14:00~15:30 北直泰(宮崎大学) 「EDFA 現象を記述する非線形シュレディンガー方程式とその解の爆発」
- 16:00~17:00 宮路智行(京都大学) 「Bifurcation analysis for the Lugiato-Lefever equation on a disk」
8月22日
- 10:00~11:30 松江要(東北大学) 「Rigorous numerics とその応用」
- 13:30~15:00 吉村和之(NTT コミュニケーション科学基礎研究所) 「非線形Klein-Gordon 型格子におけるDiscrete Breather の安定性」
- 15:30~17:00 松江要(東北大学) 「Saddle-saddle connection の精度保証付き数値計算」
8月23日
- 10:00~11:30 水町徹(九州大学) 「Asymptotic stability of solitary waves in the Benney-Luke model of water waves」
- 14:00~15:30 福泉麗佳(東北大学) 「Derivation of Bose-Hubburd model -Approximation by DNLS」
- 16:00~17:00 宮路智行(京都大学) 「Introduction to numerical simulation by spectral methods」
8月24日
- 10:00~11:30 前田昌也(東北大学) 「On weak interaction of a ground state with a nontrapping potential」
|
| 備考 |
上記プログラムは平成24年度九州大学マス・フォア・インダストリ研究所短期共同研究の採択課題である。短期共同研究に関わる費用の主な支援を九州大学マス・フォア・インダストリ研究所に依っている。
研究会の詳細は次のページに記載:http://www.imi.kyushu-u.ac.jp/joint_research/detail/20120004
|
WG番号:WG25
| 題目 |
複雑ネットワーク・サマースクール組織委員会 |
| 期間 |
H 24.3.11~H.24.9.14 |
| 責任者*と主な協力者 |
長谷川雄央*・三浦 佳二・尾畑 伸明
|
| 概略 |
複雑ネットワークは近年多くの分野で研究されている。このサマースクールでは、幾つかの分野における複雑ネットワーク研究の第一人者を講師に招き、各分野におけるネットワーク科学を研究するモチベーションと初歩的成果をレクチャーしてもらうことで、(i)この新しい分野への参入のきっかけを学生・研究者に与え、(ii) 更なる学際的研究の契機を各分野の専門家に提供することを目的とする。また、レクチャーと同時に研究会形式の研究発表の場を提供し、最新の研究成果の情報交換の場とする。 |
| 活動記録 |
2012年9月10日-12日に東北大学大学院情報科学研究科棟大講義室にてSMARTプログラム「複雑ネットワーク・サマースクール」を、2012年9月13,14日に青葉記念会館にてCMRU研究会「ネットワーク科学の数理と展開」を開催した。全体を通じての述べ参加者数は約90名となった。サマースクールはネットワーク科学分野への若手の更なる参入を促すことを目的に、東京大学増田直紀氏、大阪電気通信大学竹居正登氏によるネットワーク科学の基礎を学ぶ連続講義と、Bielefeld大学D.Volchenkov氏、北海道大学矢久保孝介氏、九州工業大学竹本和弘氏による分野紹介的なトピック講演で構成した。研究会は非線形/複雑系・物理・生物/生命科学・社会科学の各分野でネットワーク科学にちなんだ研究を行っている研究者、事業者を招聘し、お互いの分野をより知る為の学際的集いとなるよう構成した。5日間という期間に渡るプログラムにしたことによって、講義・講演から多くの事柄をじっくり学ぶ事ができたという感想をいくつか頂いた。また、本研究会は時間を共有する事による横の繋がりの形成にも役立ったようである。全体として参加した学生・研究者から多くの好評の声を頂ける研究会にすることができた。
|
WG番号:WG2
| 題目 |
光が拓く材料工学と数理科学の新接点WG |
| 期間 |
H22.12.2~H24.08.10 |
| 責任者*と主な協力者 |
久保英夫* |
| 概略 |
近年、光の特性を応用したナノスケールにおける材料工学の発展が顕著な一方で、その数理的構造の解明は不十分なのが現状である。そこで、分野横断的な交流を活性化し、新たな知見を深め、未知の構造の発掘・解析を進めることを目指す。 |
| 活動記録 |
本WGの活動の出発点は次の研究集会における異分野の研究者との交流にある:
- 青葉山勉強会「流体の方程式」(2010.6.11-12) 古川勝氏(東京大学)/ プラズマ物理
- 応用数学連携フォーラム「第13回ワークショップ」(2010.8.2)
- 下村政嗣氏(東北大学)/ バイオミメティクス
- 津田一郎氏(北海道大学)/ 脳科学
- 吉田亮氏(東京大学)/ 自己組織化マテリアル
- 上野智永氏(東京大学)/ FIS反応のパターン形成
低炭素社会の実現を促がす生物由来の次世代光学材料の数理について探求を進める:
- 応用数学連携フォーラム「第17回ワークショップ」 (2011.1.24)-- 生物規範光学材料設計について知見を深めた --
- 吉岡伸也氏(大阪大学)/ チョウの翅の微細構造と光学特性
- 不動寺浩氏(物質・材料研究機構)/ チューナブル構造色材料
- 魚津吉弘氏(三菱レイヨン)/ 蛾の目を模倣したスーパー反射防止フィルム
- 針山孝彦氏(浜松医科大学)/ 森の宝石-発色の仕組みと輝きの意味
- 日本化学会 第91春季年会(2011) アドバンスト・テクノロジー・プログラムの下村先生が組織するセッションで講演した.「数理科学とバイオミメティクス」 於 神奈川大学 2011.3.29
- 分担執筆 “数理科学と生物規範光学材料設計”, 67-70, 次世代バイオミメティクス研究の最前線-生物多様性に学ぶ-, 監修:下村政嗣/(編集)バイオミメティクス研究会,2011年
- 研究集会「EcoDesign2011 International Symposium, 7th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing」 於 京都 2011.12.1講演(査読付き講演). 題目:Mathematical physics and the moth-eye structure--モスアイ構造中の光の形態について、浅水波とのアナロジーを基に議論した--
- 応用数学連携フォーラム「第25回ワークショップ」 (2012.1.26)戸田晃一氏(富山県立大学)/ 「広田の双線形化法」の多重線形化について久保英夫(東北大学)/ モスアイ構造への数理科学的アプローチ--バイオミメティクスの紹介をし、モスアイ構造中の屈折率や量子的な効果について議論した--
- 第14回バイオミメティクス研究会 プラス ミニ国際シンポジウム 於 国立科学博物館 (2012.2.9), 逆問題の視点から観たモスアイ構造 (依頼講演)--材料表面に如何にして効率よく光エネルギーを捕捉することができるか議論した--
- 日本化学会 第92春季年会 於 慶応大学 (2012.3.26) アドバンスト・テクノロジー・プログラム「バイオミメティク材料とネイチャーテクノロジー」(下村先生が組織),モスアイ構造と逆問題について (依頼講演)--金属表面を伝播する波(プラズモン)について議論した--
- 研究打合せ 於 東北大学WPI (2012.4.10)--生物が行っている光の有効利用法に学び、その機能を具現化する構造について議論した—
「生物多様性を規範とする革新的材料技術」(研究代表者:下村政嗣先生)が平成24年度新学術領域研究に採択され、その研究グループの一つとして構成されているB01‐2班が8月10日に集まり、活動方針について話し合った。このグループは、応用数学連携フォーラム「第17回ワークショップ」に参加したメンバーを中心に組織されており、サブセルラーサイズの学理の探求とその応用を目指すこととなった。これを以て、本ワーキンググループの活動を終了する。
|
WG番号:WG30
| 題目 |
研究集会「量子確率論と量子ウォーク」組織委員会 |


| 期間 |
H 24.4.14~H24.7.5 |
| 責任者*と主な協力者 |
瀬川悦生*・尾畑伸明
|
| 概略 |
非可換な世界を記述する量子確率論で展開される独立性、極限定理、大偏差原理、グラフのスペクトルなどに関する議論の、量子ウォークへの適応の可能性を探る。
|
| 講演者 |
07/04 (水)
- 13:00~14:00
今野 紀雄 (横浜国立大学)
「量子ウォークの定常測度と極限測度」
- 14:10~15:10
吉田 裕亮 (お茶の水女子大学)
「自由確率論における組合せ論的手法」
- 15:30~16:10
佐藤 巌 (小山高等専門学校)
「量子ウォークとグラフのゼータ関数」
- 16:20~17:00
村木 尚文 (岩手県立大学)
「非可換確率論における独立性概念」
- 17:10~17:50
町田 拓也 (明治大学)
「ホインの微分方程式を通じた離散時間量子ウォークと連続時間量子ウォークの関係」
07/05 (木)
- 10:00~11:00
西郷 甲矢人 (長浜バイオ大学)
「逆正弦法則と『量子古典対応』」
- 11:10~12:10
桂 法称 (学習院大学)
「Symmetry and self-duality in discrete-time quantum walks」
- 13:30~14:10
行木 孝夫 (北海道大学)
「量子酔歩と力学系」
- 14:20~15:00
日比野 雄嗣 (佐賀大学)
「あるグラフの積に関する漸近的スペクトル分布について」
- 15:20~16:00
長谷部 高広 (京都大学)
「独立性・母関数・微分方程式」
- 16:10~16:50
樋口 雄介 (昭和大学)
「散乱行列とその周辺」
|
WG番号:WG11
| 題目 |
ハートリー方程式研究WG |
| 期間 |
H23.4.5~H24.3.31 |
| 責任者*と主な協力者 |
前田昌也*・小川 卓克・眞崎 聡
|
| 概略 |
低次元シュレディンガーポアソン系は無限遠で増大するポテンシャルをもつハートリー方程式とみなすことができる。無限遠で減収するポテンシャルをもつハートリー方程式は詳しく調べられているが増大するものに関する研究は少ない。そこで低次元シュレディンガーポアソン系の理解を目標として正のべき乗型ポテンシャルを持つハートリー方程式の解析を行う。 |
| 活動記録 |
発表論文(プレプリント)
- M. Maeda and S. Masaki “An example of stable excited state on nonlinear Schrodinger equation with nonlocal nonlinearity,” arXiv1109.2653.
- M. Maeda and S. Masaki “A survey on nonlinear Schrodinger equation with growing nonlocal nonlinearity,” preprint.
口頭発表
- 前田昌也 “増大する非局所型非線形項をもつシュレディンガー方程式について,” 応用数学連携フォーラム第19回ワークショップ, 東北大学 2011/6/8.
- 前田昌也, 眞崎聡 (講演者は前田) “A stable exicited state for negative Hartree equation,” 日本数学会秋季総合分科会, 信州大学 2011/10/1.
- 前田昌也 “On the standing waves of negative Hartree equation,” 第98回神楽坂解析セミナー, 東京理科大学 2011/10/22.
活動成果:
低次元におけるシュレディガーポアソン方程式の一般化となる無限遠で増大するポテンシャルを持つハートリー方程式について局所適切性, 定在波解の安定性解析を行った.
この研究により今まで知られていなかった高エネルギーにもかかわらず安定となるソリトン解の存在が示された. この結果は今までの予想(高エネルギーのソリトンは全て不安定)を覆し, 数学, 物理学ともにあまり注目してこなかった高エネルギー解が実は解の挙動, 物理系の性質に対して重要な役割を担っている可能性があることを示唆している.
|
WG番号:WG7
| 題目 |
低混雑度ネットワーク設計WG |
| 期間 |
H23.4.1~H24.3.3 |
| 責任者*と主な協力者 |
大舘陽太* |
| 概略 |
構造的グラフ理論の手法を用いて、ネットワークを模倣する低混雑度・低密度のサブネットワーク設計に対する高速アルゴリズムを与える事を主目的とする。 |
WG番号:WG6
| 題目 |
数学・数値解析学・生物学の連携によるパターン形成のメカニズム解明WG |
| 期間 |
H23.4.1~H24.3.1 |
| 責任者*と主な協力者 |
鈴木香奈子* |
| 概略 |
自然界に見られるパターン形成のメカニズム解明に向けて、反応拡散系の解析からアプローチを行う。数学、数値解析学、生物学の連携による新たな研究分野確立も目指す。 |
WG番号:WG24
| 題目 |
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 短期共同研究「大規模ネットワークの特徴を抽出するアルゴリズムの開発と社会行動の予測」組織委員会 |
| 期間 |
H 23.9.30~H 24.2.10 |
| 責任者*と主な協力者 |
長谷川雄央*・大舘陽太・鈴木香奈子・三浦佳二・尾畑伸明
|
| 概略 |
ネットワークの理論的な研究を行っている研究者、実データに基づいた研究を行っている研究者、実際使用する立場にある企業の人間が集まり、お互いの知識と問題意識を共有、解決していくことで、ソーシャル・ネットワークを例とする大規模ネットワークの特徴を効率的に抽出するアルゴリズムの提案や人間の社会行動の数理の研究の発展、新しいviral marketingやrecommendationの提案へと繋がる研究を発展させる。
|
| 活動記録 |
2011年2月6日~10日、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所にて短期共同研究「大規模ネットワークの特徴を抽出するアルゴリズムの開発と社会行動の予測」を実行。下記公開プログラムでそれぞれの研究課題について紹介し、そこで出てきた問題について議論、研究シーズを探った。
公開プログラムとして研究会「ソーシャル・ネットワークの構造とダイナミクス~ヒトの社会活動の理解予測に向けて」を開催した。プログラムの直接参加者は15名。また、月・火・木・金の講演についてはUSTREAMによる中継を行った。USTREAMライブ配信の合計ユニーク視聴者数は81となった。期間を限定して録画を公開しているが、2012年2月12日現在の4講演の合計録画視聴者数は66となっている。
|
| 備考 |
上記プログラムは平成23年度九州大学マス・フォア・インダストリ研究所短期共同研究の採択課題である。短期共同研究に関わる費用の主な支援を九州大学マス・フォア・インダストリ研究所に依っている。
研究会の詳細は次のページに記載:http://www.imi.kyushu-u.ac.jp/events/view/761
|
WG番号:WG23
| 題目 |
CMRU研究会「ネットワークから見る生命」組織委員会 |
| 期間 |
H 23.6.1~12.23 |
| 責任者*と主な協力者 |
長谷川雄央*・大舘陽太・鈴木香奈子・三浦佳二 |
| 概略 |
ネットワーク科学と生命科学の融合的研究を促進するべく、関連する研究者を招聘し、研究会を開く。具体的にはタンパク質相互作用ネットワーク、代謝ネットワーク、遺伝子転写ネットワーク、振動子、の4つのトピックについてそれぞれの専門家を学外から招聘し、導入から最新の成果までのレクチャーを受ける機会を設ける。
|
| 研究会 |
2011年12月21日~23日、情報科学研究科5F小講義室にて開催。研究者を学外から4名、学内から2名招聘して研究会を行った。活発な議論のある研究会となり、参加者だけでなく、講演者間でも多くの情報交換の場となった。直接の参加者は20名、USTREAMによるインターネット中継の(ユニーク)視聴者は34名となった。
詳細はフォーラムページに記載。
|
WG番号:WG16
| 題目 |
画像処理とコンピュータビジョンの数理的側面(MAIPCV)ウィンタースクール実行委員会 |
| 期間 |
H 23.5.17~H 24.3.31 |
| 責任者*と主な協力者 |
出口光一郎*・宮岡礼子・尾畑伸明・徳山豪・岡谷貴之・儀我美一(東京大学)・泉屋周一(北海道大学)・利根川吉廣(北海道大学) |
| 概略 |
画像処理とコンピュータビジョンの数理的側面(MAIPCV)ウィンタースクールを以下のように開催した。
| セミナー名称 |
Mathematical Aspect of Image Processing and Computer Vision (MAIPCV) Winter School 2011
 |
| 実行委員会 |
|
出口光一郎、尾畑伸明、宮岡礼子、大舘陽太、三浦佳二
|
| 概要 |
|
博士課程学生を中心とする若手研究者26名(公募)に対して、外国からの招待を含む講師6名による画像処理とコンピュータビジョンの数理的側面についてのセミナーを、2011年11月24日(木)~26日(土)の間、東北大学青葉記念館(5階会議室)において行った。
|
| 支援 |
| 東北大学重点戦略支援プログラム「数学をコアとするスマート・イノベーション 融合研究共通基盤の構築と展開」、東北大学情報科学研究科、東北大学理学研究科 |
プログラム |
24日(木) Mathematical aspects of Computer Graphics
- 10:00-12:00 安生健一(株式会社オー・エル・エム・デジタル)
- 13:30-16:30 Konrad Polthier (ドイツ、Berlin Freie大学 教授)
25日(金) Variational Methods for Computer Vision
- 9:00-12:00 梶原 健司(九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授)
- 13:30-16:30 Ernie Esser(米国、カリフォルニア大学アーバイン校 研究員)
- 17:00~ 懇親会
26日(土) Optimal Estimation for Computer Vision
- 9:00-12:00 金谷健一(岡山大学自然科学研究科 教授)
- 13:30-16:30 Sami Brandt(フィンランド、Oulu大学/デンマーク、コペンハーゲン大学 教授)
|
| 出席者 |
| 約40名(内参加学生26名) |
|
WG番号:WG1
| 題目 |
数理生物学研究集会組織委員会 |
| 期間 |
H22.12.1~H23.11.24 |
| 責任者*と主な協力者 |
高木泉*・小谷元子・鈴木香奈子 |
| 概略 |
Heidelberg大学の数理生物学を中心とする応用数学者のグループと本学の数学者及び他分野研究者との共同研究を推進するため、数理生物学研究集会を開催する。 |
| 活動記録 |
2011年11月21日から24日まで仙台国際センターにてHeidelberg大学等から8名の海外研究者を招き,"Mathematical Models of Biological Phenomena and their Analysis"を開催した.Heidelberg大学から2名,Warsaw大学から2名,Wroclaw大学から1名,本学から4名,国内他大学等から6名が講演し,8名がポスターによる発表をした.62名の参加を得た.
詳細は開催時のHP参照.
|
| 特記事項 |
Heidelberg大学からの参加者から帰国後,今後の協力体制構築に向かって具体的に検討したい旨,提案があった. |
WG番号:WG19
| 題目 |
東北大=北大 数学連携
Summer Institute 2011 組織委員会
 PDFファイル PDFファイル |
| 期間 |
H 23.6.13~8.24 |
| 責任者*と主な協力者 |
三浦佳二*・鈴木香奈子・長谷川雄央・大舘陽太・尾畑伸明 |
| 概略 |
東北大 x 北大 数学連携 Summer Institute を以下のように開催した。
| シンポジウム名称 |
東北大 x 北大 数学連携 Summer Institute
 |
| シンポジウム趣旨 |
| 東北大の数学連携推進室の構成員が北大にて講演することで、
北大の数学連携研究センターの構成員との議論・交流を促すことを目的とした。
単に大震災の影響を避けて北大に滞在するというだけではなく、
普段会わない人が活発に議論する“Virtual Summer Institute”として機能することを目指した。
|
| 組織委員会 |
| 三浦佳二・鈴木香奈子・ 大舘陽太・ 長谷川雄央・尾畑伸明 |
招待講演 |
4件
-
三浦 佳二
(東北大学 大学院情報科学研究科 数学連携推進室)
イベント発生時刻の不規則性
-
鈴木 香奈子
(東北大学 大学院情報科学研究科 数学連携推進室)
発癌メカニズムを記述するある反応拡散系の解がつくる空間パターンの安定性
-
大舘 陽太
(東北大学 大学院情報科学研究科 数学連携推進室)
Designing low-congestion sparse networks
-
長谷川 雄央
(東北大学 大学院情報科学研究科 数学連携推進室)
ユークリッド格子から遠く離れて: Nonamenable Graph と Complex Network の相転移
|
| 出席者 |
| 約15名 |
|
WG番号:WG4
| 題目 |
情報科学研究科CMRU発足記念
シンポジウム実行委員会
 PDFファイル PDFファイル |
| 期間 |
H 23.1.10~2.24 |
| 責任者*と主な協力者 |
尾畑伸明*・田中和之・木下賢吾・桑原雅夫 |
| 概略 |
情報科学研究科数学連携推進室(Collaborative Mathematics Research Unit)発足記念シンポジウムを以下のように開催した。
| シンポジウム名称 |
CMRU-Symposium: Mathematical Models and Simulations for Real World Networks
 |
| シンポジウム趣旨 |
| 実世界ネットワークのモデル化とシミュレーションを基軸とした数理的研究を分野横断的に推進するため、外国招待研究者2名を加えた諸分野研究者によるシンポジウムを開催して、多角的な討論と情報交換をする機会を設ける。数学連携推進室の発足(平成23年1月1日)を受けて、本研究科重点研究プロジェクトの連携を築き、分野横断的な研究シーズ探索を狙う。これによって、研究科の研究活動を強化することができる |
| 組織委員会 |
| 尾畑伸明・田中和之・桑原雅夫・木下賢吾 |
| 支援 |
- 東北大学重点戦略支援プログラム
「数学をコアとするスマート・イノベーション 融合研究共通基盤の構築と展開」
- 東北大学情報科学研究科重点研究プロジェクト
「多様なセンサー情報を融合した 道路交通流のナウキャストとフォアキャスト」
- 東北大学情報科学研究科重点研究プロジェクト
「生命情報ビックバン時代の生命 情報科学研究の基盤構築」
|
| 招待講演 |
3件
- Philippe Blanchard
Faculty of Physics and ZiF, University of Bielefeld Inhomogeneous Random Graph Models and Generalized Percolation and Epidemic Processes
- Matsuyuki Shirota
Graduate School of Information Sciences, Tohoku University Information Theoretic Background of Statistical Potentials of Protein Structures
- Cyril Furtlehler
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA), Sacley, TAO Project-Term Learning Multiple Belief Propagation Fixed Point for Real Time Road Traffic Inference
|
| 出席者 |
| 約50名 |
|